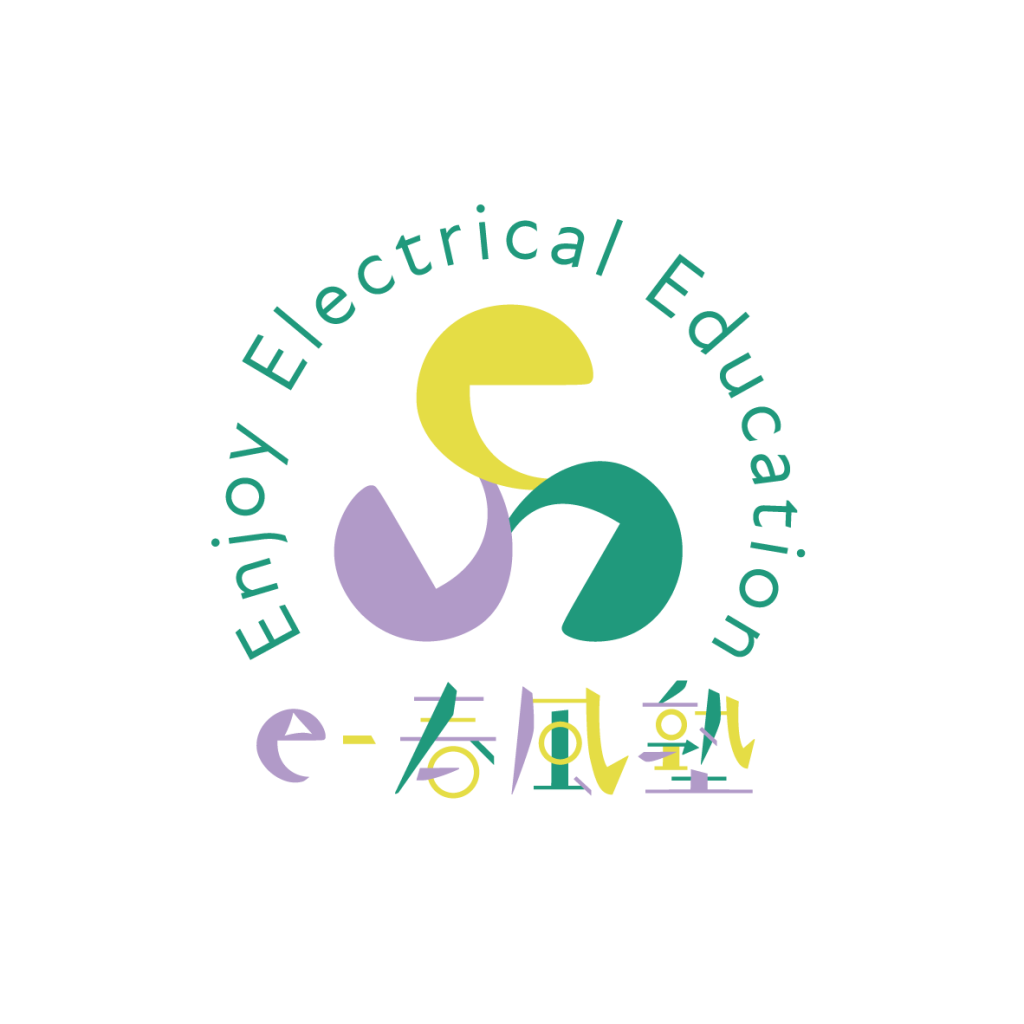e-春風塾で主要5教科(国語、数学、英語、理科、社会)の学習指導を開始してから約2か月。利用してくださる生徒さんも増え、e-春風塾に新しく、学習塾としての一面が定着しようとしています。
しかし、「プログラミング塾なのに、なぜ主要5教科の学習指導を?」「一般の学習塾と何が違うの?」と、疑問や不安を感じている方も多いはず。そこで今回は、e-春風塾の代表であり、文系講師の1人でもある沢津橋先生(以下、つばっしー先生)に、学習指導部門立ち上げにあたっての思いを伺ってきました。
-学習指導部門を立ち上げようというのはプログラミング専門塾としては思い切った施策だと思いますが、どういった思いが背景にあるのでしょうか?
「僕が中学時代に通っていた塾と似たような形の学びが、e-春風塾なら提供できるなぁと思ったのが大きいですね。以前のインタビューでも少しお話したんですが、僕が中学3年の夏から半年だけ通った学習塾は、教室長がその後もずっーと、15年くらい変わらなかったんですよね(笑)。普通に40教室以上ある塾なので、普通は異動があるんでしょうが、なぜか僕のところの校舎だけなく。当時の先生が本当に最近まで在籍されたりしていて、僕にとって高校、大学、社会人になっても『変わらず戻って来られる場所』だったんです。変わらず長く付き合っていくことで親しみや愛着が湧くというか。
この部分がe-春風塾の今の風景と重なるように感じたんです。小学校3、4年生くらいの頃から塾に来ていた子たちが今中学校に上がって、今、学校のテストで良い点を取ろうと頑張る姿を見られるようになったことに感動して。昔はすごいフザけてたのに(笑)。これなら長年の愛着を前提にした学習が提供できるかもしれないと思って、今回の立ち上げに踏み切りました。」
以前つばっしー先生にお話を伺った時の記事はこちらから♪↓
-愛着、というと?
「長い時間一緒に過ごす中で育まれる親しみを持って教育に携わりたい、という感じです。元々僕は18歳の頃から30歳になるまでずっと大学院や、社会人になってからは投資会社の仕事とすら並行しながら週末に塾講師をやっていたんですが、主に中学3年生を相手に受験対策のクラスを担当していて、1年で担当が変わる環境だったんです。もちろん受験生なので、その時間はとても濃密なものではあったんですが、1年間で終わってしまうということに一抹の儚さを感じていて。そういう時間軸を超えた教育活動がしたいなと思っていました。」
-確かに1年間というと、ようやく慣れてきた頃に解散、という形になってしまうことも多いですよね。
「はい。それから、僕は春風塾のことを『学習塾』というよりは『私塾』だと思っています。違いは何か?一般の学習塾は「システム」とか「環境」とか「カリキュラム」を価値ある点として訴求します。『私塾』はそれより、「個人としての教師」がむき出しなイメージです。すでに小学生のうちから、講師とお子さんの関係性があるのも踏まえ、愛着と親しみを持って学べる場所であるべきだと思っているんです。学校の先生とも親とも違う立場の人と、『評価』されることもなく、『斜めの関係』を結ぶことができる場所。そういう相手だからこそ話せることもあると思うんですよね。だから、先生から一方的に評価や成績を付けられるのではなく、先生と親しみを持って一緒に学び続けることができる環境を作りたいと思いました。」
-なるほど。先生と生徒さんの距離が近く、親しみやすい環境で学べるというのは、プログラミングの指導からも感じられる気がします。
「e-春風塾の講師と生徒さんの間には長い時間プログラミング指導を通して培ってきた信頼がありますから、この親しみや愛着は強く感じられるのではないかと思っています。僕たちの会社名も『株式会社イトシィ』で、実は『愛しい』と『糸島』を掛けた会社名になっているんです。だから塾全体としても、愛着という部分はかなり大事にしていきたいと思っています。こうした学習環境を通して、自分らしい学びにも繋げていってもらえたら更に良いですね。」
-自分らしく伸び伸びと学べると、勉強も楽しくなりますよね。実際、学校ではテストの点数や順位、内申点といった評価を窮屈に感じてしまう生徒さんもいると思います。
「そうですね。小学校や中学校の頃に大切にすべきことの1つは『疲れさせすぎないこと』だと思うんですが、今の日本の教育はそこがあまり実現できていないように感じます。
現代の日本は、勉強に限らず、若年時の『手段』が目的化しやすい傾向にあります。例えばある競技を習い始めたとして、それを通して体力や精神力を付けたり人間関係を構築したりすることが目的で、その手段として試合を行っているのに、試合に勝つことが目的になって追い込みすぎてしまう、というようなイメージです。こうなると、精神的な目標を作ることができずに疲弊してしまいます。そうではなく、人生の岐路に立った時に自己実現するための精神的余力を残せるように、詰め込みすぎず疲れさせない環境作りが必要です。」
-手段が目的にならないように、という指導はよく聞きますが、日本全体の傾向になっているのは驚きです。どうしてそうなってしまうのでしょうか?
「大学の時に社会学をやっていたので、そこで見聞きした議論を紹介すると、一説には、日本では日常生活と宗教的文化の間にあまり日頃から強い結びつきがないからですかね。欧米はキリスト教が生活に強く根付いているので、神学的な考えに基づいて精神的な目的を作りやすいんです。でも日本はそうじゃないので、達成しようとする種目その物自体が目的化、言い換えれば偶像化しやすいんです。」
-なるほど。学校の勉強でも、テストで良い点を取ったり、良い学校に進学したりすること自体が目的になってしまっていることはよくありますね。
「はい。そうなるとただ勉強量を増やすことになり、疲れてしまいます。本来勉強は『よく学びよく生きるための基礎作り』であるべきなんです。ただ公式や単語を覚えてテストで良い点数を取ることを目指すのではなく、伸び伸びと向き合ってほしい。そのためにも、愛着のある指導形態を届けたいと思っています。かといって何となく緩い雰囲気でやるのではなく、基礎学力はしっかりと向上させていくつもりです。」
-でも、そうした勉強の本質を追求して伸び伸びと勉強することと、基礎学力を確実に向上させることを両立するのは、なんだか難しそうに聞こえますが…
「実際、二つの側面の両立を図るのは絶妙で、簡単ではないと思います。塾としてもこのバランスをどう取っていくかは常に考えています。でも、e-春風塾ならではの愛着を生かして、生徒さんの個性やペースを尊重しながら学習できる環境を提供したい、という思いは変わりません。でもただ楽しくおしゃべりしながら勉強する、というわけではなく、しっかりと基礎学力は上げられるように工夫をして*、信念をもって取り組んでいます(*次回インタビュー記事にて掘り下げ予定)。それを皆さんにも知っていただけたら良いなと思いますね。」
-なるほど。強い信念のもとに、学習指導部門は立ち上げられていたのですね。つばっしー先生、ありがとうございました!
取材&記事制作 ゆずか記者(保坂柚花 九州大学文学部3年)
(取材日2025.6.11)